|
日本のきものには長い長い歩みがありました。「そこにきものがあるから着る」のではなく、「きものを着 る私は美しい」という永遠のテーマにたどりつかなければなりません。私たちの祖先が、遠い昔人間らしい生 活を初めた時から衣服は常に私たちとともにありました。むろん、そこには第一に風土に適合するように、活 動しやすいように、また階級を表わすことなども含まれました。第二として、着て美しいこと、衣服そのもの の美、たとえば色彩、文様、素材、形態などの美です。大局的に見れば、それらは日本の自然の美、日本の風 土の産物かもしれませんが、私たちの祖先が工夫に工夫を重ねてきたということは、その時代時代を行きてき た人間の心をよく表現しているのではないでしょうか。そういう意味からも歴史ときものは密接につながりが あります。衣服を見て生活様式を知り、文化を知る。その逆もいえるのです。原始時代から今日まで衣服の歴 史はまことにめまぐるしく慌ただしい。そこから私たちはきものの心を汲み取り、理解したいのです。この素 晴らしい民族衣裳であるきもの、単に衣服の変遷を学ぶだけでなく、きものの着方なども折り込みながら、ひ と味違った服飾史にしたいと思っております。 |
| 原始時代 |
|---|
| 縄 文 時 代 | 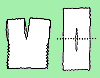 紀元前七千五百年頃からで狩猟、漁勞を生活の糧とし、住まいは竪穴住
紀元前七千五百年頃からで狩猟、漁勞を生活の糧とし、住まいは竪穴住居と呼ばれるもので、海辺では貝塚が作られ、また山岳地においても大規 模な集落が営まれ、そこに素朴ながら生活をより豊かにという願望からか、 素晴しい土器、土偶、貝や動物の骨で作ったアクセサリーなどが作られま した。そして出土した土偶から衣服をまとっていたと考えられます。その衣 服は「貫頭衣(かんとうい)」といって、仮に一幅の布があれば、真ん中に穴を開けて頭を出し、両腕 が出るようにして脇を縫って着用していたことは間違いないものと思われます。 その素材は、鹿、熊、 猪、兎などの毛皮をなめしたり、木の皮をはいで何回もたたいて作った布のようなのもを、骨の針で綴 じ合わせたりしたようです。そして、この時代の衣服はおしゃれではなく、身を守るための必需品だっ たのです。アクセサリーすら護身用として身につけていたのです。 |
|---|---|
|
弥 生 時 代 | 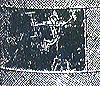 縄文時代の狩猟期に続いて、紀元前二、三百年頃から紀元後三百年頃までを
縄文時代の狩猟期に続いて、紀元前二、三百年頃から紀元後三百年頃までを弥生時代といいます。稲作を中心とする農業が開始され、日本農耕文化が始ま った時代です。同時に大陸から鉄器、青銅器などがもたらされ、またその製造 なども伝えられ、製作もされるようになり、あわせて金属器時代ともいわれて います。 衣生活の状態はどうだったのでしょうか。この時代は縄文時代に比べ、少しではありますが資料があ ります。その一つ、香川県から出土した銅鐸(弥生時代の民族が儀式に使った祭器だろうといわれてい るもの)に描かれた絵で、狩りとか、臼を中心に穀物をつく姿などがあります。しかし、この絵は線画 でそのうえ簡略化したものなので、その生活程度から推し計れば、絶対裸体ではなく何らかの着装がな されていたはずです。 そしてもう一つ、信憑性の高い資料があります。それは「魏志倭人伝」によるもので、これは「三国 志」という中国正史の一つである書で、三国時代(二二〇〜二八〇)のことを記述した書物で、「魏志 倭人伝」は「魏志」の巻三〇の「東夷伝」のなかの倭人に関する部分で、倭(日本)人の社会状態、風 俗、習慣などを詳しく記し、日本への道程とか方向なども書かれているのですが、そのなかに服飾につ いて書かれている部分があります。 「男子皆露介、以木緜招頭、其衣横幅、但結束相連、略無縫、婦人被髪屈介、作衣如単被、 穿其中央、 貫頭衣之」すなわち男子は皆髪を結び、布で頭を巻いて、その衣服は幅広の布を縫わずに身体にまとっ ている。婦人は髪を曲げ結んで、衣服は一枚の布のような形に作られ、中央に穴をあけて頭を通して着 ている、とあります。 つまり、男子は横幅衣と呼ばれるもので一枚の布を肩から垂らして腰に巻く巻衣であり、女子は頭を 通し、両脇を腰下くらいまで縫ったものを着ていたと書かれています。しかし、男子が貫頭衣を着なかっ たとは書かれていないところから、男子も時によって巻衣と貫頭衣を使い分けていたのではなかったか と思われます。そして女子の貫頭衣も、縄文時代に比べて丈が長くなったのではないかと思われます。 そして衣服の素材も獣毛皮に加えて、植物性の繊維織物(麻、紵麻など)とか絹織物などが使われま した。それは、静岡県の登呂遺跡から木製の織機の断片が出土したことからもうなずかれます。 この時代のアクセサリーは、ガラス製の玉を連ねたネックレス、貝の指輪、青銅製の腕輪や指輪、こ とに指輪は、この時代から近世に至るまでほとんど全くなかったといわれていますが、面白い現象です ね。いずれにしても、南方の国々との交渉があったことから、衣服もおのずから南方系の衣服に似てい たと思われます。 |

